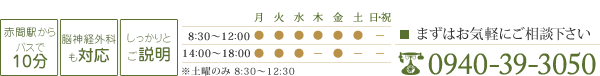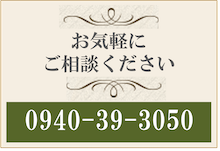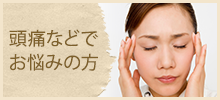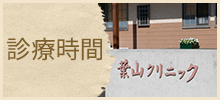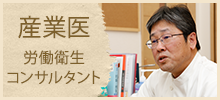宗像市葉山クリニックの撫中です。かつて京都に「伝説」の予備校があった。京大・国公立医学部に毎年300人以上の合格者を出し 京都大学医学部・京都府立医科大学の合格者の3割以上を占めていた時期もあり、京大受験・難関校に強い予備校として知られていた。昭和40年代から60年頃までが、合格実績のピークであった。当時は、理科3クラス、医科1クラス、文科1クラスで合計1300名の定員であった。しかし、三大予備校が全国展開するようになり、京都ローカルの予備校として劣勢となり、少しずつ合格実績は悪化していった。(Wikipediaより抜粋)
1982年 (昭和57年度) 在籍定員1300名中 合格実績 (在籍者のみ、講習のみ受講は含めず)
京大合格者 265名(医 36名、薬8名、理24名、農30名、工112名、法23名、経18名、文11名、教3名)
医学部合格者 347名
小生も1979-1980年の1年間在籍していた。合格実績は上記と同様と記憶している。先日、同予備校の同窓会があった。同じアパートで、同予備校に在籍した仲間たちである。まず、予備校卒業してから、31年目に第1回を実施、立て続けに3回までは開催したが、コロナのパンデミックで今回8年ぶりの開催となった。13人がアパートに在籍、今回は9人出席、3人は都合がつかず、欠席であった、。あと一人の方の消息が依然不明である。たった1年間のつながりで、しかも浪人生であり、そこまで会話もしていなかったのに、未だに集まってその当時の記憶をたどる会がひらけることは非日常であり、とても幸福感に満ちた時間である。仲間たちも異口同音に「この会が一番楽しい。同窓会の中でも最優先だ。」という。全員が今あるのはこの浪人時代が決めたと思っている。結果が出てよかった、と今でも痛感する。表題の「伝説」というのは、帰路の新幹線のなかで検索してはじめて知ったことであるが、渦中にいたときは意識したことはなかった。今思えば、狂気に満ちた成績だ。思い出話は尽きず、5年後に次回開催を約束し、解散した。と同時にグループラインでまだ過去のいろいろな出来事の答え合わせが進行している。何とも愛おしい会である。